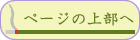お寺のデータ
- 所在地
- 奈良県奈良市西ノ京町457
- アクセス
- 近鉄橿原線「西ノ京」下車徒歩2分
- 宗派
- 法相宗大本山
- 山号
- 創建
- 680(天武9)年、天武天皇が菟野皇后(後の持統天皇)の病気平癒を願って創建を発願。697年、持統天皇により本尊開眼。
- 本尊
- 銅造薬師三尊像(国宝)
- 線香
- 瑠璃光、吉祥香、宝相華、京桜、春陽、微笑、淡墨桜
- 初訪問日
- 1994年4月16日
- 公式サイト
- https://yakushiji.or.jp/
- 備考
- 西国四十九薬師霊場第1番、神仏霊場会(奈良県12番)、南都七大寺、要拝観料(600円?)
平成10年ユネスコ世界遺産登録
-

孫太郎稲荷神社
南門を出て踏切を渡った南側にある神社。
-

休ヶ岡八幡宮
こちらも南側の神社。薬師寺を守護するために寛平年間(889~898年)に大分県宇佐から現在地に勧請された。
-

西塔と南門
-

勧進所
-

東院堂
東院堂での法話
「情思(じょうし)」…後悔する前に情思する。
「意乗(いのり)」…朝必ずいのりをする。
-

龍王社
-

東院堂(鎌倉時代・国宝)
養老年間に吉備内親王が元明天皇の冥福を祈って発願建立された。天禄4年(973年)に火災で焼失、現在のものは弘安8年(1285年)に再建されたもの。
-

地蔵菩薩と不動明王
東院堂の裏におられました。
-

中門(二天門)
中門は昭和59年(1984年)に復興。二天様は平成3年(1991年)復興のニューフェイス。持国天(右)と増長天(左)のパターンのようですね。
-

東回廊
-

東塔(白鳳時代・国宝)
これだけが創建当初から残っているもの。 高さ約34m。各層の間に”裳階(もこし)”がついているため六重塔のように見えるが、実際は三重塔である。 フェノロサが”凍れる音楽”と評したという話は有名。
薬師寺東塔の内陣には、四天王に守られたガリガリの釈迦如来(苦行釈迦如来坐像)が安置されている。
-

西塔
昭和56年再建。453年ぶりに東西の塔が揃った。
-

金堂
昭和51年再建、二重二閣、五間四面、瓦葺き(裳階付)で「龍宮造り」と呼ばれる。
金堂・東塔・西塔を回廊がぐるりと取り囲む「薬師寺式伽藍配置」。 -

金堂正面の灯籠
-

金堂(側面)
薬師寺は天武天皇の発願により、もとは”飛鳥”の地に建てられたが、 平安遷都に伴い718(養老2)年に現在の地に建立された。 飛鳥の城殿(きどの)には”本薬師寺”跡が残されている。
-

大講堂
正面41m、奥行20m、高さ17m。ご本尊は弥勒三尊像(白鳳時代・重要文化財)。後堂には仏足石と21首の和歌が刻まれた仏足石歌碑(いずれも天平時代・国宝)が安置されている。
-

大講堂(左)と金堂(右)
-

東回廊と中門(奥)
中門をくぐり、西塔前あたりから撮影。
-

鐘楼と東僧坊
-

聚賓館
大宝蔵殿の隣の聚賓館が特別公開されていたので覗いてみました。
-

聚賓館の前あたり
お百度石がありました。
-

食堂(じきどう)跡
大講堂の裏側あたり。
-

不動堂
西僧坊の裏にひっそりとあります。
-

ムラサキシキブ
-

與楽門(北門)
近鉄「西の京」駅からだとこちらの門が近いです。
玄奘三蔵院
-

お写経道場
北門を出ると、右手に門がある。
-

薄墨桜
-

礼門
まっすぐ進むと礼門。
-

本坊事務所(お写経道場)
-

礼門
-

玄奘塔
平成3年(1991年)建立。法相宗の始祖である玄奘三蔵の遺骨が収められている。
-

玄奘塔
この日は特別公開で拝観の人で賑わっていた。
-

大唐聖域壁画殿
平成12年(2000年)に、平山郁夫画伯が30年の歳月をかけて描いた壁画を絵身舎利として祀ったもの。
-

玄奘塔(裏側)